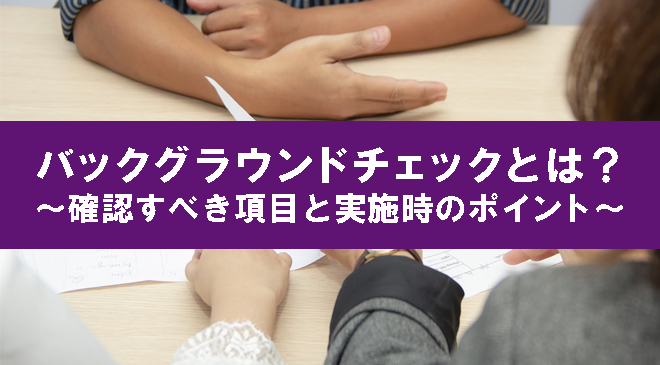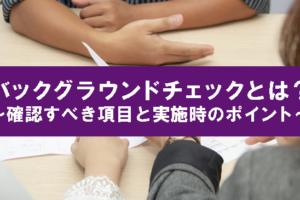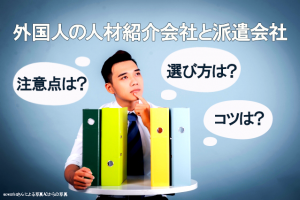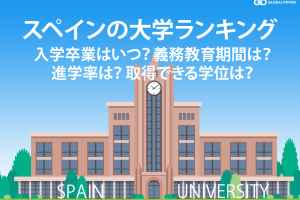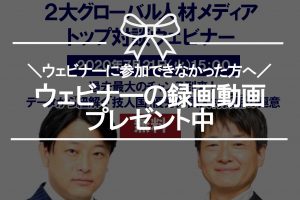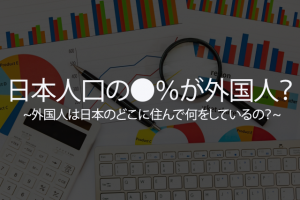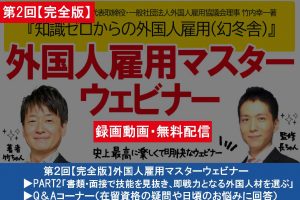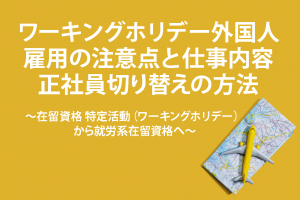採用活動においては、候補者の経歴や人物背景を正確に把握することが非常に重要です。
特に外国人雇用では、在留資格や就労条件の確認も必要となり、通常の履歴書や面接だけでは見落としがちなリスクが存在します。
そこで活用できるのが、バックグラウンドチェックです。
本記事では、採用前調査の概要や確認すべき主な項目、調査を実施する際のポイントなど、企業が安全かつ適切な採用判断を行うための情報を解説します。
バックグラウンドチェックとは?

バックグラウンドチェックとは、狭義では採用候補者の犯歴確認のことです。
広義では、交通違反歴、民事訴訟歴、学歴 、職歴、ソーシャルメディア分析、クレジットレポートの確認を含みます。
バックグラウンドチェックを行う目的は、ミスマッチや不正リスクを未然に防ぎ、安心して雇用できる人材を確保すること。
従来日本ではあまり浸透していませんでしたが、近年は外国人雇用の増加やグローバルな人材流動に伴い、信頼性確保やコンプライアンス対応の観点から、その必要性が徐々に認識されつつあります。
日本におけるバックグラウンドチェックの制約と背景

日本ではバックグラウンドチェック用の公共インフラという概念自体が欠如し、法的にも採用時調査の重要性が認識されていません。
結果として、制度的かつ網羅的な実施は難しい状況です。
ここでは、バイリンガル興信所Japan PIの代表、本記事の筆者である小山の知見をもとに、他国の状況と比較しつつ、日本のバックグラウンドチェックの現状を整理します。
制度インフラの国際比較
英語圏諸国(米国、カナダ、豪州)では、政府・警察による犯歴データベースの自己開示制度が確立されており、個人が自身の犯歴を確認できます。
米国では犯歴、交通違反歴、民事訴訟歴、学歴、職歴、クレジットレポート等の個別データベースが整備され、開示条件をクリアすれば各データベースにアクセス可能です。
一方、日本では警察庁が犯歴の自己開示制度を設けておらず、本人でも自身の記録を確認できない秘密主義体制となっています。
例外的に海外移住時のビザ取得など国外での必要性が認められる場合のみ、厳格な審査を経て犯歴証明書を発行しています。
日本における確認手段の限界
実名報道された事件について、メディアデータベースを通じた犯歴確認が部分的に可能だが、報道基準が曖昧で網羅的な確認は困難です。
広義のバックグラウンドチェックに含まれるクレジットレポートは、貸金業者専用で取引・採用目的での利用は不可、民事訴訟記録も氏名・名称からの検索システムが存在しません(最高裁判決除く)。
法的責任概念の相違
欧米諸国では過失雇用(Negligent Hiring)の概念が定着しており、従業員がトラブルを起こした場合に雇用者の責任が問われますが、採用時に十分な注意(バックグラウンドチェック等)を払えば責任が免除されます。
日本でも民法715条の「使用者責任」により、従業員の不法行為が事業に関連していれば企業は損害賠償責任を負います。
しかし、欧米の過失雇用概念とは異なり、採用前の調査を行っていたかどうかで責任が左右されるわけではありません。
採用後の教育や業務監督など、従業員の行動を適切に管理することに重点が置かれています。
バックグラウンドチェックの調査項目

バックグラウンドチェックは、制度が整っていない日本でも、可能な範囲で候補者の経歴や信頼性を確認する手段として活用できます。
法的・制度的な制約があるため、場合によっては、専門家(探偵や弁護士)に相談しながら進めることが推奨されます。
主に以下のような項目を中心に調査します。
・学歴・職歴
・在留資格
・犯歴・訴訟歴
・反社会的勢力との関わり
学歴・職歴
候補者が提示する履歴情報の信頼性を確保するためには、学歴・職歴の確認が欠かせません。
具体的には、卒業証明書や学位取得証明を通じて学歴の正確性を検証したり、過去の勤務先に在籍実績を照会して職務内容や雇用期間を確認したりします。
場合によっては、前職の上司や同僚へのリファレンスチェックを実施し、仕事ぶりや人物像を把握するケースも。
学歴・職歴のチェックにより、経歴詐称や不正な資格申告を防ぎ、採用判断の精度を高めることが可能になります。
在留資格
外国人労働者を採用する際に特に重要なのが、在留資格の確認です。
就労可能な資格を持っているか、また資格の期限がいつまでかを把握することで、法的に正確な雇用ができるかを判断できます。
在留カードやパスポートを提示してもらい、あわせて資格外活動の有無も確認しておくことが必要です。
近年はグローバル人材の採用が増えているため、在留資格の適切なチェックを怠ると、企業側に法令違反のリスクが及ぶ可能性も。
在留資格は、採用時に必ず確認すべき基本項目と言えるでしょう。
犯歴・訴訟歴
犯歴や訴訟歴の確認は、採用リスクを軽減するための重要なプロセスです。
履歴書上の自己申告だけでなく、公開情報を活用して、刑事事件や民事訴訟への関与の有無を調査します。
たとえば、過去に窃盗や暴力事件を起こしていないか、労務関連のトラブルや契約違反がないかといった点が確認されます。
これにより、職場内でのトラブルやコンプライアンス違反のリスクの未然回避が可能に。
採用後に不適切な経歴が発覚すれば企業の信用低下につながるため、慎重なチェックが欠かせません。
反社会的勢力との関わり
候補者が反社会的勢力と関わりを持っていないかどうかを調べる「反社チェック」も重要な工程です。
過去に所属していた団体や組織の調査、公開情報や専門データベースの照会を通じて、暴力団や違法組織との関与がないかを確認します。
従業員の反社会的勢力との関わりが発覚した場合、企業は大きな法的・社会的リスクを負う可能性も。
そのため、多くの企業では、コンプライアンス体制の一環として反社チェックを徹底しており、安全かつ健全な組織運営のために欠かせない調査項目と言えるでしょう。
調査を実施する際のポイント

バックグラウンドチェックを行う際は、法的リスクや個人情報に配慮しながら、適切なプロセスで進めることが重要です。
ここでは、押さえておきたい3つのポイントを解説します。
・候補者の同意を取得する
・公開情報を活用する
・リファレンスチェックと併用する
候補者の同意を取得する
バックグラウンドチェックを実施する際は、まず候補者から事前に同意を得ることが欠かせません。
本人に無断で調査を行うと、プライバシー侵害や法的トラブルに発展する恐れがあります。
そのため、調査の目的や範囲、確認する項目を明示した上で、書面や電子同意を取得することが理想的です。
特に外国籍の候補者の場合、母国の法制度や個人情報保護規制が絡むこともあるため、透明度の高い手続きを徹底することが重要です。
信頼関係を損なわずに調査を進められるよう、候補者の理解と納得を得ることを心がけましょう。
公開情報を活用する
バックグラウンドチェックでは、新聞記事や官報、裁判記録、SNSなどの公開情報を活用することも重要です。
これにより、候補者が申告した経歴や資格に誤りがないかを確かめられるほか、犯歴や訴訟歴、反社会的勢力との関わりといったリスク要因も外部の情報源から確認することができます。
ただし、インターネット上の情報は真偽が不明な場合も多く、誤解や偏見につながるリスクも。
そのため、複数の情報源を組み合わせて裏付けをとることが大切です。
公開情報を適切に活用することで、効率的かつ客観的なバックグラウンドチェックを実現できます。
リファレンスチェックと併用する
バックグラウンドチェックをより精度高く行うためには、前職の上司や同僚から直接評価を得る「リファレンスチェック」との併用が効果的です。
経歴やスキルだけでなく、実際の勤務態度や人柄、チームへの貢献度など、書類やデータからは見えにくい情報を収集できます。
特に管理職や専門職の採用においては、過去の職務遂行能力を第三者の視点から確認することが有効です。
ただし、調査先への連絡は、候補者の同意を得た上で慎重に進める必要があります。
リファレンスチェックを取り入れることで、採用の判断材料が一層充実し、ミスマッチ防止につながります。
まとめ
今回は、バックグラウンドチェックの重要性、国内での導入状況、法的留意点などについて解説しました。
適切にバックグラウンドチェックを行うことで、候補者の経歴や素行を正確に把握し、雇用後のトラブルや採用ミスマッチを防ぐことが可能です。
特に、外国人雇用においては、在留資格や資格外活動の確認なども含めたリスク管理が欠かせません。
採用リスクを最小限に抑え、安全な雇用環境を構築するためにも、バックグラウンドチェックの導入を検討してみてはいかがでしょうか。